- 最近、お城がブームみたい
- お城に行きたいけれど、どこが良いかわからない?
- お城について、あまり知識がない
こんな悩みをかかえていませんか?
近年、マスコミやSNSなどでもお城ブームが起こっています。
動画や写真集でも日本の四季を彩るお城は、美しく華やかな景観を見せてくれます。
きれいなお城に行って、写真を取ったり景色を味わったりしたいけれど、どのお城に行けば良いのかわからない人もいますよね。
そこでこの記事では、京都府在住でお城好きの私が実際に足を運んだ中から、是非おすすめしたい【京都・兵庫版】魅惑のお城をご紹介します。
この記事を最後まで読めば、次のお休みにはワクワクしながら、お城に向かっていますよ!
【京都・兵庫版】魅惑の城5選!
今やお城人気は、老若男女を問わず全国的なブームとなっています。
数ある全国のお城の中でも、京都府と兵庫県には、名だたるお城が存在しています。
その美しさであまりにも有名なお城や、幻想的な景観を誇るお城、歴史的意義の高いお城など魅力が満載。
それでは「時代を越えた魅惑の城!おすすめ5選」をご紹介しましょう。
- 京都「二条城」
- 京都「福知山城」
- 兵庫「姫路城」
- 兵庫「竹田城」
- 兵庫「篠山城」
1.京都「二条城」

最初にご紹介するのは、有名な世界遺産の「二条城」です。
 さとし
さとし「唐門」の重厚で豪華な格式の高さに、徳川幕府の威信を感じます。
- 二条城は、1603年(慶長8年)に江戸幕府初代将軍の徳川家康が、天皇在住京都御所の守護と将軍上洛時の宿泊所として築城しました。1626年(寛永3年)3代将軍家光の時代に、後水尾天皇の行幸に伴う大改修により、現在の規模になっています。
- 1867年(慶応3年)に、15代将軍徳川慶喜により二の丸御殿にて「大政奉還」の意思が表明されたのは、歴史上大変大きな出来事といえます。
- 1994年(平成6年)には、ユネスコ世界遺産として登録されました。
- 唐門は二の丸御殿の正門。四脚門で屋根の前後に唐破風(からはふ)を備え、最も格式が高いといわれています。冠木(かぶき)の上は、龍・虎や鶴・亀・松竹梅などの豪華けんらんなモチーフが刻まれています。
- 二の丸御殿は入り母屋造本瓦葺で城内最大の建物(国宝)。江戸幕府の終えんを表明した「大政奉還」の舞台として、あまりにも有名です。
《基本情報》
| 正式名称 | 元離宮二条城(もとりきゅうにじょうじょう) |
| 住所 | 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 |
| アクセス | 京都市営地下鉄「二条城前」駅下車徒歩すぐ |
| 営業時間 | 8:45~16:00(開城17:00) 「二の丸御殿」8:45~16:10 |
| 定休日 | 12/29~31日 |
| 「二の丸御殿観覧休止日」 | |
| 1・7・8・12月の火曜日、12/26~28日、1/1~3日 | |
| ご利用料金 | 「入城料・二の丸御殿観覧料」 一般1,300円、中高生400円、小学生300円 |
| 「入城料のみ」一般800円、中高生400円、小学生300円 | |
| 駐車場 | 第一駐車場(二条城東側) |
| 営業時間(8:15~18:00) | |
| 収容台数(乗用車120台、バス11台) | |
| 駐車料金(乗用車2時間まで1,200円、以降1時間ごと300円) | |
| (バス2時間まで、予約ありの場合3,000円、予約なしの場合3,300円) |
《交通アクセス》
2.京都「福知山城」

本能寺の変で有名な明智光秀が築いた、北近畿で唯一天守閣のある福知山城です。
 さとし
さとし天守閣から望む由良川の眺望は見事です。
- 織田信長の命により、1579年(天正7年)に丹波を平定した明智光秀が、西国攻略の拠点として福知山城を築きました。光秀は初代城主となり、娘婿の明智秀満を城代に置き、統治したのです。
- 本能寺の変後、羽柴秀長ら数々の城主を経て、1669年(寛文9年)に朽木(くつき)氏が城主となり、明治維新まで約200年13代にわたり福知山を治めました。
- 明治まで存続した福知山城は、1873年(明治6年)の廃城令で天守が取り壊されます。しかし、昭和後期に天守再建の市民活動が高まり、「瓦一枚運動」による市民の寄付金にて、昭和61年11月に再建されました。
参考:福知山城公式ホームページ
- 「福知山城の景観」は、見る角度によって様々な表情を見せています。東西から見ると大きく、南北側からは細長い形に見えます。左右対称ではない個性的な形状を持っているのです。
- 「石垣」は、自然石を積み上げた「野面積み」であり、石材は墓石や石仏・五輪塔などの「転用石」が大量に使われ、再建時の発掘調査では500個余りが確認されています。明智光秀の合理的な側面が見受けられます。
参考:福知山城公式ホームページ
《基本情報》
| 名称 | 福知山城(ふくちやまじょう) |
| 住所 | 京都府福知山市字内記5 |
| 開館時間 | 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |
| 休館日 | 毎週火曜日(祝日の場合は翌日)/12月28日~31日、1月4日~6日 |
| 入館料 | 一般券(個人)おとな330円、こども110円/共通券(個人)おとな480円、こども190円 ※共通券は、隣接「福知山市佐藤太清記念美術館」の入館料とセット(割引) |
| 駐車場 | 無料(ゆらのガーデン駐車場) |
| 車:約70台、バス:5台(要予約) | |
| 電車でお越しの場合 | 京都駅からJR山陰本線(特急)で約1時間15分、大阪からJR福知山線(特急)にて約1時間30分 JR・京都丹後鉄道「福知山駅」から徒歩15分 |
| お車でお越しの場合 | 国道9号の福知山市街地方面から東堀交差点を右折、府道55号を約1kmで福知山城へ |
《交通アクセス》
3.兵庫「姫路城」

「白鷺城(はくろじょう)」と呼ばれ、しらさぎが羽を広げたような美しい姿と、雪化粧をまとったような鮮やかな白さが際立つ世界遺産・国宝の姫路城です。
 さとし
さとしとにかく真っ白で、きれいなお城に見とれてしまいます。
- 姫路城の発端は、1333年に反鎌倉幕府として挙兵した赤松則村(あかまつのりむら)が姫山に砦を築いたのが始まりです。その後、息子の赤松貞範(あかまつさだのり)が1346年に姫路城の基礎となる城を築いたとされています。
- 1600年関ケ原の合戦後、池田輝政(いけだてるまさ)が城主を受け継ぎます。当時、輝政は徳川家康から西日本における豊臣方の大名をけん制するよう命を受けていました。重大拠点としての姫路城の大改修に着手し、9年後に完成します。
- 1617年に城主となった本多忠政(ほんだただまさ)は、西の丸・三の丸を増築し、今日にまで引き継がれる形態となるのです。
- 太平洋戦争の戦禍を逃れた姫路城は、1956年(昭和31年)から「昭和の大修理」が始まり、8年を要して完了します。
- 1993年(平成5年)、日本の建造物として初めてユネスコ世界遺産に登録されました。
参考:姫路城公式サイト
- 「大天守」は姫路城のシンボルで代表的な建造物。「白鷺城」の名にふさわしい、華麗であざやかな美しい白を基調とした外観は、ユネスコにおいて「木造建築の最高の位置」と評されています。5層の屋根で、地下1階・地上6階の造りになっています。
- 「小天守」は天守台の上で、大天守の横に連なり、「西小天守」・「東小天守」・「乾小天守」の3つの小天守があります。特に「乾小天守」は、天守台の西北隅(乾の方角)に位置し、最も高い建物になります。
- 「菱の門」は姫路城内で、最大の門です。櫓門(ひもん)と呼ばれる二の丸入り口の門で、両柱の上の冠木(かぶき)に木彫りの「菱の紋」があり、名前の由来になっているのです。門全体に安土桃山時代の様式を残しています。
参考:姫路城公式サイト
《基本情報》
| 名称 | 姫路城(ひめじじょう)別名「白鷺城(はくろじょう)」 |
| 住所 | 兵庫県姫路市本町68番地 |
| 開城時間 | 午前9時~午後5時まで(閉門は午後4時) |
| 休城日 | 12月29日・30日 |
| 入城料金 | 大人(18歳以上)1,000円、小人(小学生・中学生・高校生)300円 |
| *小学校就学前、無料 | |
| (好古園との共通券) | 大人(18歳以上)1,050円、小人(小学生・中学生・高校生)360円 |
| 駐車場 | 姫路市まちづくり振興機構の「姫路城周辺駐車場」のご案内を参照 |
| JR姫路駅、山陽姫路駅から徒歩20分 |
《交通アクセス》
4.兵庫「竹田城」

ご存じ、「天空の城」で人気が爆発した幻想的な名城「竹田城」です。
 さとし
さとし天空の眺望は、時代を越えた夢幻の世界です。
- 竹田城は、1443年頃(嘉吉年間)に当時の但馬守護、山名宗全の重臣、太田恒氏に命じて築かせたとされています(口碑)。1580年(天正8年)羽柴秀吉の但馬攻めで落城しました。
- 1585年(天正13年)に城主となった赤松広秀の時代に大改修が行われ、現在に残る石垣の遺構は、その当時に整備されたものと考えられています。
- 関ケ原合戦の時、赤松広秀は西軍に加わりますが、後に東軍に寝返り、鳥取城を攻めます。しかし、城下町に放火したとの罪で自刃させられ、武田城は廃城となりました。
参考:竹田城の歴史|朝来市
- 「石垣」:竹田城の見どころは、何と言っても当時を彷彿とさせる圧倒的な存在感の石垣遺構です。縄張り(城の敷地)は、天守台を中心に「くの字型」の連郭式に配置され、当時の状態を完全に残しているのも大きな魅力です。
- 「天守台からの眺望」:天守台から南千畳を見下ろす景観は、まさに「日本のマチュピチュ」といえます。
《基本情報》
| 名称 | 竹田城(たけだじょう)、別名「虎臥城(とらふすじょう)」 |
| 住所 | 兵庫県朝来市和田山町竹田古城山169番地 |
| 入城期間・時間 | (春)スプリングシーズン/3月1日~5月31日、午前8時~午後6時 |
| (夏)サマーシーズン/6月1日~8月31日、午前6時~午後6時 | |
| (秋)雲海シーズン/9月1日~11月30日、午前4時~午後5時 | |
| (冬)ウインターシーズン/12月1日~翌年1月3日、午前10時~午後2時 | |
| ※1月4日~2月末は、冬季閉山につき入城できません | |
| 観覧料金 | 大人(高校生以上)500円/中学生以下、無料 |
| 年間パスポート1,000円(毎年4月1日~翌年3月31日) | |
| お車でお越しの場合 | 北近畿豊岡自動車道・播但連絡自動道の「和田山IC」が最寄りのICです IC下車後、「和田山IC前」信号を左折、約10分ほどで各駐車場へ(アクセスガイド) |
《交通アクセス》
5.兵庫「篠山城」

「天下普請」(てんかふしん)による15カ国20諸大名の動員で、山陰道の拠点として築かれた篠山城です。
 さとし
さとし築城の名手、藤堂高虎によって築かれた「高石垣」の堅牢さが伝わってきます。
- 篠山城は、1609年(慶長14年)に徳川家康が天下支配を強固にし、西日本の豊臣家諸大名を抑えるため、山陰道の要衝に築いた城です。
- 6ヶ月ほどの短期間に実戦向きの城として築かれたので、天守閣はありませんでした。二の丸には、京都二条城の遠侍と呼ばれる建物に類似する「大書院」が建てられています。当時の一大名の書院としては、例のない威風堂々とした建物といえます。
- 「大書院」は、1994年(昭和19年)1月6日に火災により消失してしまいます。その後、市民の熱い願いと寄付により2000年(平成12年4月)に再建されました。
- 「大書院」:篠山城といえば、代表的な建物として「大書院」が有名です。書院造りの御殿ですが、徳川幕府の「天下普請」により築城されただけに、その規模と建築様式は破格のものとなっています。幕藩体制の間、篠山藩の公式行事などに使用されました。
- 「高石垣」:築上の名手藤堂高虎によって築かれている篠山城は、石垣も「高い石垣」によって防御し、反りの少ない乱積みで、下部には「犬走り」と呼ばれるスペースが設けられています。
- 「馬出し」:〈城の出入口の外側に作られた防御用の曲輪(くるわ)〉が、東・南入口に「角馬出し」として、ほぼ完全な状態で残っています。
《基本情報》
| 名称 | 篠山城(ささやまじょう) |
| 住所 | 兵庫県丹波篠山市北新町2-3 |
| 開館時間 | 午前9時~午後5時(受付終了午後4時30分) |
| 休館日 | 毎週月曜日、年末年始(12月25日~翌年1月1日)※祝祭日は開館、翌日休館 |
| 大書院入館料 | 大人400円、高校・大学生200円、小・中学生100円 |
| 歴史4館 | (篠山城大書院、武家屋敷安間家史料館、青山歴史村、歴史美術館) |
| 共通入館券 | 大人600円、高校・大学生300円、小・中学生150円 |
| ※共通券は2日間有効、ただし、2日目が休館日の場合は当日のみ有効 | |
| ※歴史美術館が特別展開中は、4館共通券の料金が異なる場合があります | |
| ※天守台・本丸・二の丸は無料開放 | |
| 駐車場 | 有料駐車場あり |
| 電車でお越しの場合 | JR福知山線「篠山口駅」から神姫グリーンバス篠山営業所行「二階街」バス停下車徒歩5分 |
| お車でお越しの場合 | 舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口I.C」より東へ約10分で篠山城跡へ |
《交通アクセス》
お城人気3つの理由
お城といえば、遠い過去の遺産。かつては、一部のお城好きマニアで人気のイメージがありました。
しかし、現在では歴女の急増や若い世代にも大きく広がりを見せています。
お城の楽しみ方は、時代と共に多様化しています。自分流の楽しみ方を追求すれば、自然にお城の良さがわかってくるのではないでしょうか。
それでは、人気の理由は何があるのか、順番に見ていきましょう。
「日本100名城」とスタンプラリーの普及
お城ブームの契機になったのは、2006年に公益財団法人日本城郭協会による「日本100名城」の選定が大きく影響しているといえます。「日本100名城」が謳われ、お城好きマニアには一つの指標ができたのかも知れません。
さらに、2007年には、「日本100名城公式ガイドブック」スタンプ帳つきが発売され、スタンプラリーを楽しみながらお城巡りを楽しむ人が急増したのです。
観光としてお城を楽しむ、スタンプラリーを目標にしてお城巡りをする、お城の知識を増やしたいなど楽しみ方の幅が増えたといえます。
SNSやお城アプリで人気拡大
もう一つの要素として、SNSの普及やお城アプリの開発などにより、お城の良さをあと押している背景があります。インスタグラムやツイッターなどにお城の写真を投稿すると多くの人に情報交換されたり、お城の良さが広がっていきます。
姫路城では、「姫路城大発見アプリ」を使用すると、城内のARスポットでスマホやタブレットをかざせば、動画や写真とともに解説が出てきて楽しめるようになっています。
他にも、100名城の詳細な内容を確認できるアプリやスタンプラリーのようにお城を攻略するゲームアプリなど、様々なアプリが開発されてお城人気に拍車をかけているのではないでしょうか。
お城とイベントの融合

近年では、お城と様々なイベントを融合して、来場者数を増やしたり、町おこしを図ったりする自治体も増えてきています。
中でも、お城をバックに音楽コンサートを開催したり、お城にプロジェクションマッピングを仕掛け、さらに幻想的で魅力的な世界を演出したりしています。
マニア的なお城ファンだけではなく、老若男女幅広い層を対象にした新しいお城ファンの発掘が、お城人気をさらに盛り上げていくと考えられます。
お城の楽しさを知って時代を行き来しよう!
ここまで、【京都・兵庫版】時代を越えた魅惑の城】について見てきました。ご紹介した5選のお城で、その魅力についておわかりいただけたのではないでしょうか。
ここでご紹介しましたのは、数あるお城の中でも、ごく一部となります。
とにかく、「お城の楽しさとは、自分で現地へ足を運び、自分の五感でその場の景色を感じる」が原点ではないでしょうか。
そのためには、まず行きたいと思ったお城へ足を運びましょう!
その先には自分だけの楽しみが待っていますよ。
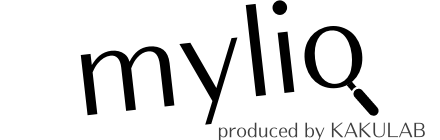

コメント